ヨーロッパ時代のアラン・スキッドモア
(存在しないCD復刻シリーズのためのライナーノーツ)
イギリスのテナー・サックス奏者アラン・スキッドモアのキャリアには、70年代後半から80年代にかけて、大きな空白があると考えられてきた。この沈黙期間を経て、彼の音楽には「かつての切れ味がなくなった」と評する人もいる。だが、スキッドモアがその間、まったくの新天地に活動の場を移し、さまざまな名義で10枚近いアルバムを発表していたとしたら? そこには以前にも増して熱く研ぎ澄まされた、炎のような演奏が記録されているとしたら?
このシリーズは、再発売もCD化もされたことのないこれらのアルバムを録音順に集大成し、アラン・スキッドモアという稀代のジャズ演奏家の真価を、改めて世に問うためのものである。
[1] European Jazz Quintet
"Live at Moers Festival" (Ring/Moers Music MOMU 01018)

rec. 1977/05/29
Alan Skidmore (ts), Gerd Dudek (ts), Leszek Zadlo (ts),
Ali Haurand (b, perc), Pierre Courbois (ds, perc)
[2] European Jazz Concensus
"Four for Slavia" (MRC 1C 066-32 855)

rec. 1977/06
Alan Skidmore (ts, ss), Gerd Dudek (ts, ss, shenai),
Adelhard Roidinger (b), Lala Kovacev (ds)
[3] Skidmore/Dudek/Roidinger/Kovacev
"Morning Rise" (Ego 4006)

rec. 1977/09
Alan Skidmore (ts, ss), Gerd Dudek (ts, ss),
Adelhard Roidinger (b), Lala Kovacev (ds)
[4] European Jazz Quintet
"European Jazz Quintet" (Ego 4012)

rec. 1978/11
Alan Skidmore (ts, ss), Gerd Dudek (ts, ss), Leszek Zadlo (ts, ss),
Ali Haurand (b, perc), Pierre Courbois (ds)
[5] Alan Skidmore/Tony Oxley/Ari Haurand
"S.O.H." (Ego 4011)
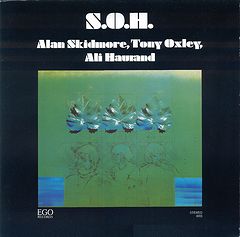
rec. 1979/02
Alan Skidmore (ts, ss), Ali Haurand (b), Tony Oxley (ds)
[6] SOH (Skidmore/Oxley/Haurand)
"SOH" (View VS 0018)

rec. 1981/04/25
Alan Skidmore (ts, ss), Ali Haurand (b), Tony Oxley (ds, perc)
[7] Third Eye
"Third Eye Live!" (View VS 0021)
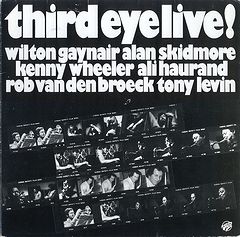
rec. 1982/01/13
Alan Skidmore (ts), Wilton Gaynair (ts), Kenny Wheeler (flh),
Rob van den Broeck (p), Ali Haurand (b), Tony Levin (ds)
[8] European Jazz Quintet
"III" (Fusion 8010)

rec. 1982/02/16
Gerd Dudek (ts, ss), Leszek Zadlo (ts, ss), Alan Skidmore (ts, ss),
Ali Haurand (b), Pierre Courbois (ds)
本シリーズは以上8枚から成るが、ぜひ追加しておきたいものとして、2007年に発掘リリースされた下記のCDがある。録音順からいっても、これが(今のところ)この時代の最後の1枚ということになる。
[9] S.O.H. (Alan Skidmore/Tony Oxley/Ali Haurand)
"Live in London" (Jazzwerkstatt JW 016)

rec. 1983
Alan Skidmore (ts, ss), Ali Haurand (b), Tony Oxley (ds, perc)
amazon.co.jp
1942年生まれ、ロンドン出身のアラン・スキッドモアは、英国トラッド・ジャズのサックス奏者ジミー・スキッドモアを父に持ち、十代でプロ活動を開始。65年にアレクシス・コーナーのグループで録音デビューする。ジャズ演奏家としては、69年から72年にかけて20枚以上の先鋭的アルバム(自身のリーダー作2枚を含む)に参加。台頭する英国ジャズ新世代の逸材として注目された。
74年にはジョン・サーマン、マイク・オズボーンとともにサックス・トリオ S.O.S. を結成。75年からはエルトン・ディーンのグループ Ninesense に参加し、やがて双頭アルバム『El Skid』(エルトン+スキッドモアの略)の制作に至る。だがこれを録音した77年を最後に、イギリスのジャズ界からアラン・スキッドモアの姿は消えてしまう。「カムバック作」として知られているのは、88年に録音された18年ぶりのリーダー作『Tribute to 'Trane』である。
だがこの間、スキッドモアは音楽活動の中心を西ドイツに移していた。ベース奏者アリ・ハウランド(1943年生まれ、ドイツ出身)と組んで、ハウランドが始めたヨーロッパのジャズ演奏家のゆるやかな集合体(現在はユーロピアン・ジャズ・アンサンブルと名乗っている)に参加。6年の間に、自らがリーダーもしくは共同リーダーとなる上記のアルバム8枚を次々に録音する。これらはいずれもミュンヘンやハンブルクやベルリンのマイナー・レーベルから発売されたため、ヨーロッパ・ジャズのファン以外にはほとんど知られることがなく、他国盤が出ることもなかった。
追加の1枚を含めた9枚のアルバムは、3つのグループによって録音されている(1枚を除く)。
テナー・サックス+ベースとドラムズのトリオ「S.O.H.」で3枚。
テナー・サックス2本+ベースとドラムズのカルテット「ユーロピアン・ジャズ・コンセンサス」で2枚。
テナー・サックス3本+ベースとドラムズのクインテット「ユーロピアン・ジャズ・クインテット」で3枚。
要するに、ホーンもピアノも抜きで、無骨なまでにテナー・サックスの可能性を追求した編成ばかりということになる。残る1枚は、ピアノ入りのグループ「サード・アイ」だが、スキッドモアによるメンバー紹介を聞く限り、ここでも共同リーダー的な役割を果たしたようだ。
アルバム [5] [6] [9] の S.O.H. は、スキッドモア、オクスレー、ハウランドの頭文字を取ったトリオ。泣く子も黙る英国フリー・ジャズのトップ・ドラマー(のひとり)トニー・オクスレー(1938年生まれ、イギリス出身)と、多彩な技を持つアリ・ハウランドのベースをバックに、スキッドモアがワン・ホーンでじっくりと吹きまくる。スキッドモアの語彙、構成力、集中力がもっともよくわかる編成。他のアルバムはサックス奏者が複数いるため、気を抜いて聴いていると誰のソロだかわからなくなるが、その点この3枚はわかりやすく聴きやすい。
アルバム [2] [3] はユーロピアン・ジャズ・コンセンサス。 [3] はメンバー4人の名義だが、同一グループと考えていいだろう。アラン・スキッドモアと、独フリー・ジャズ第一世代として活躍したゲルト・デュデック(1938年生まれ、ドイツ出身)がフロントに並ぶ双頭グループだが、録音はこの2枚しか残されていない。ベースは、このころよく山下洋輔と共演していたアデルハルト・ロイディンガー(1941年生まれ、オーストリア出身)。アタックの強いドラムズでフロントを煽るララ・コヴァチェフは、ユーゴスラビア出身で、ビッグ・バンドを中心に50年代から活躍してきたベテランだという。この2枚のアルバムで聴ける東欧的なエキゾティズムも、コヴァチェフの存在と関連がありそうだ。
アルバム [1] [4] [8] のユーロピアン・ジャズ・クインテットは、ヨーロッパ時代のアラン・スキッドモアが、もっとも長期間(少なくとも6年間)維持することのできたグループ。スキッドモア、ゲルト・デュデックに、レスゼク・ザドロ(1945年生まれ、ポーランド出身)を加えたフロントで、3人全員がテナーとソプラノ・サックスを持ち替えながら、ヘヴィ級の演奏を聴かせてくれる。ベースはアリ・ハウランド。サックス3人の大暴れを前に一歩も引かないドラムズはピエール・クールボワ(1940年生まれ、オランダ出身)。クールボワは、ギュンター・ハンペル・グループとフリー・ミュージック・クインテットでESPレーベルに録音を残したあと、自らのグループ、アソシエーションP.C.を結成した、勃興期のフリー・ジャズとジャズ・ロックの両方に足跡の残る重要人物である。
サックスの3人がそれぞれソロをとるだけでなく、サックス・アンサンブルとして集団即興の可能性が追求されているのもこのグループの聴きどころ。スキッドモアがかつてマイク・オズボーン、ジョン・サーマンとともに結成したグループ S.O.S. の発展形と見ることもできる。シンセサイザーや多重録音を駆使する S.O.S. の音楽性は、(その後の3人の活動を考えると)サーマンの主導だったように思われがちだが、スキッドモアもサックス3人という編成にこだわりがあったのではないか。
アルバム [7] のサード・アイは、ベースのアリ・ハウランドのグループで、ここではゲストとして、ケニー・ウィーラー(1930年生まれ、カナダ出身)、ウィルトン・ゲイナー(1927年生まれ、ジャマイカ出身)が加わっている。
ちなみに、この時のピアノはロブ・ヴァン・デン・ブルック(1940年生まれ、オランダ出身)、ドラムズはトニー・レヴィン(1940年生まれ、イギリス出身)だが、これにアラン・スキッドモアとゲルト・デュデックを加えた5人が、現在ではユーロピアン・ジャズ・クインテットの名を引き継いでいる。そう、驚くなかれ、彼らは2009年の今も全員が健在で、一緒に演奏活動を続けているのだ。
ここから先はまったくの推測になるが、アラン・スキッドモアが「ヨーロッパ時代」を過ごすことになった理由を考えてみたい。
イギリスで、シリアスなジャズの担い手として60年代末に登場したスキッドモアは、同世代の僚友たちとともに注目を集め、いきなりデッカ、フィリップスという二大メジャー・レコード会社で自身のリーダー・アルバムを制作する幸運に恵まれる。
ジョン・コルトレーンの音楽に大きな影響を受け(エルヴィン・ジョーンズとはのちに親交を結んでいる)、69年にはアート・アンサンブル・オブ・シカゴと共演し、70年にはソフト・マシーンの、71年にはウェザー・リポートのホーン・セクションとして録音やツアーに参加したスキッドモアは、これらの多彩な経験を次作に生かせるはずだった。だが、70年代の音楽産業は巨大化、寡占化の一途をたどり、メジャー・レーベルにシリアスなジャズの居場所はなくなってしまう。
端的に言えばジャズでは食えなくなったわけで、同世代の仲間たちも、アメリカで成功したジョン・マクラフリンや、のちにECMの専属アーティストになるジョン・サーマンを除けば、みな自主独立の活動へと沈潜していくことになる。
そんな中では、ジャズ以外のライヴやスタジオの仕事をコンスタントに続けていたスキッドモアの状況はまだましなほうだったかもしれない。デビュー以来一貫して、英国R&Bシーンでの演奏、ポップスのスタジオ録音に参加しており、『ブルースブレイカーズ・ウィズ・エリック・クラプトン』のサックスも、ケイト・ブッシュの「サキソフォン・ソング」のサックスも、40年前からジョージー・フェイムのバンドでサックスを吹いているのもスキッドモアなのだから。
レコード業界の大きな変化にともなう70年代のこうした苦況は、イギリスだけに限らず、またジャズだけに限らず、多くの音楽家が経験したものだろう。そうした中にあって、30代なかばのアラン・スキッドモアが、経済的な安定よりも音楽家としての発表の場を求めて、新天地に活動の中心を移した――移さざるを得なかった、というのが「ヨーロッパ時代のアラン・スキッドモア」の真相なのではないか。
60年代末から音楽祭などでたびたび西ドイツを訪れていたスキッドモアは、同地に熱心なフリー・ジャズ愛好家の多いことを知っていたし、ロルフ・キューンやフォルカー・クリーゲルのアルバムに参加したことで、ヨーロッパの演奏家との切磋琢磨も経験済みだった。 [1] を聴くとき、そこに新たな仲間と聴衆を得て好きな音楽に邁進できる喜びが溢れているように聞こえるのは私だけだろうか。
あくまで個人的な体験だが、1984年の春から秋にかけて、ロンドンで数週間暮らした時、ロニー・スコッツ・クラブや100クラブに足繁く通ったが、アラン・スキッドモアの姿や名前をついぞ見た記憶がない。もちろん当時はまだスキッドモアのことなど何も知らず、それどころか大勢のイギリスのジャズ演奏家をこのとき初めて知ったのだが、その中に地元っ子のスキッドモアがいなかったことは、今になって考えてみると不思議で、やはり完全にイギリスを離れていたのではないかと思える。
86年ごろからロンドンのジャズ・シーンに復帰したスキッドモアは、その後、現在までに7枚のリーダー・アルバムをコンスタントに発表している。メジャー・レーベルと再契約する機会はついぞ訪れていないが、昨今の情勢では、音楽家よりも先にレコード会社のほうが消滅しそうである。そして例えば、アラン・スキッドモア・カルテットによって05年に録音されたジョン・コルトレーンの曲「Lonnie's Lament」は、24年前に S.O.H. で録音された同曲と、方法は違っても同じぐらいの感動で迫ってくるのだ。
投稿時間 : 00:00 個別ページ表示 | トラックバック (0)
「添野君、ヴァンダーなんとかっていうサックスの人、知ってる?」と、ある人から訊かれたのは一昨年のこと。「知ってるもなにも、ケン・ヴァンダーマークだったら96枚ぐらいレコード持ってますよ!」と威勢よく答えたわけだが、なんでもドキュメンタリー映画祭のコンペ部門に、ヴァンダーマークを撮った映画の応募があったのだという。
そんなわけで、そういう作品があることは早くから知っていて、見たくてたまらなかったのだが、昨年いくつかの映画祭で上映され、先月ついに米本国でDVD化されたこれを、ようやく見ることができた。
"The Work Series: Musician" (Facets Video DV96157/2008)

amazon.co.jp
ケン・ヴァンダーマークをかんたんに紹介すると、フリー・ジャズの演奏家で、シカゴ在住の白人男性で、テナー・サックス、バリトン・サックス、クラリネット、バス・クラリネットを主に演奏し、数えきれないほどのグループや企画を主宰し、(フリー・ジャズや即興音楽の世界では)国際的な人気があるが、いまだ来日したことがない、という人である。私も生演奏に接したことはない。
個人的には、90年代の一時期まったくジャズを聴かなくなっていた私を、レコードを通じて引き戻してくれた恩人のひとりであり、それ以来のファンなのだが、この人のすごいところは、とにかく多作なことで、聴き続けているとあっという間にCD棚が埋まってしまう。毎月のように新作・参加作のアルバムが出ていて、中には2枚組、3枚組、ひどいときは12枚組(!)もあるという情け容赦のなさ。それでも、どのアルバムもそれぞれ工夫が凝らされ、ていねいに作られていて聴きでがあるから、やめられない止まらないのである。
このドキュメンタリー映画『ミュージシャン』は、06年ごろのヴァンダーマークに密着取材した作品で、ダニエル・クラウスというドキュメンタリー映画作家の「仕事」シリーズ第2弾として製作された。「保安官」「音楽家」と来て、次作は「大学教授」というシリーズなのだが、別に職業紹介が目的ではなく、どれも特異な人物ありきでその仕事に迫るという内容になっているようだ。
本篇58分、ヴィスタ・サイズ、HDヴィデオ撮影で、DVDはスクイーズ収録。NTSCのみだが、リージョン・オールの英語字幕付きということで、世界中で見てもらうことを想定した仕様になっている。聴き取りの苦手な日本人としては、英語字幕は最高にありがたい。
特典として、本篇で使われなかったシーンがこれまた60分近く付いており、ノーカットの演奏シーンも含まれる。音楽ファンにとっては、ほとんど2時間近いてんこ盛りの内容と言える。
全体は「作曲」「スタジオ」「ツアー」「家族」など11章に分かれており、スクールデイズ、ポール・ニルセン=ラヴとのデュオ、FME、パワーハウス・サウンド、CINC、ソロなどさまざまな編成での演奏シーンが次々に飛び出してくる。CINCでの北米ツアーが一応の山場になっているが、映画全体としては、音楽にもインタビューにも偏ることなく、人物をじっと見つめて、そこから何かを感じ取らせるという手法が貫かれている。最前からこれを「音楽ビデオ」ではなく「ドキュメンタリー映画」に分類しているのは、この手応えがはっきりしているからに他ならない。
レコードから聞えるもの、そこから私の中にできあがっていたケン・ヴァンダーマークという人の人物像を超えるものは、ここにはない。しかし意外性がないからといって、この映画が薄っぺらな出来というわけではまったくない。それどころか、100枚のアルバムを聴いてきたのと同じ印象を1時間で得られるのだから、優れたドキュメンタリー映画の力というのは、やはり大したものなのだ。
ここに映っているのは、つねに疲れきって、睡眠不足で、いらだっている一人の男の姿である。40代になったばかりの彼は、いらだちを静かに押し殺しながら、作曲して、練習して、リハーサルをして、録音して、スケジュールを立てて、ツアーに出て、インタビューに答えている。DIYに徹した活動ぶりと、そうでなければやっていけない「フリー・ジャズ」演奏家の生活の厳しさに驚く人もいるかもしれないが、それはこのジャンルの聴き手なら先刻承知のこと。問題はなぜそこまでして、多岐にわたる活動を続けるのか、倦まず弛まずライヴとレコード制作に邁進するのか、であり、1時間の映画を最後まで見ることで、その答えが「音楽家」と「音楽」の関係にあることがわかってくる仕掛けになっている。
そこで初めて『ミュージシャン』という題名の意味と普遍性が浮かび上がってくるのだが、だからといって撮影の対象が誰でもよかったというわけではなく、これはやはり、ケン・ヴァンダーマークという特異な音楽家がいてこそ成立した映画なのだ――というのは贔屓の引き倒しだろうか。
そのほか、わかっていたはずでも、改めて印象づけられたのは、作曲を重視するヴァンダーマークの姿勢。即興で演奏することと同じぐらい、作編曲へのこだわりがあり、この2つが2本の柱のように彼の音楽活動を支えている。そんな印象が得られたのは収穫だった。
未使用シーンの中には、本篇には登場しない、テリトリー・バンドのリハーサル風景や、ヴァンダーマーク5、ブリッジ61といった編成での演奏が含まれている。音楽ファンとしてはもちろんうれしい付録なのだが、これらの撮り方や、撮っておいて使わなかった選択基準をみても、映画の作り手の目的意識の高さ、明解さがよくわかる。ダニエル・クラウスというこの監督の今後も、要注目だろう。
Ken Vandermark 本人のサイト
http://www.kenvandermark.com
Ken Vandermark のディスコグラフィ
http://tisue.net/vandermark/
Daniel Kraus と Work Series のサイト
http://www.workseries.com
投稿時間 : 06:33 個別ページ表示 | コメント (0) | トラックバック (0)
その後ようやく聴いたアンドリュー・ヒルの『Time Lines』はなるほど傑作で、そうなると新録旧録とりまぜて近年たくさん出ている彼のCDをどれも聴きたくなってしまうわけですが、まあガツガツしてもしょうがないのでゆっくり参りましょう。
ユニクロからECMのアルバム・ジャケットをプリントしたTシャツが発売されています。前からあったのかもしれませんが、私は数日前の新聞広告で初めて知りました。
http://store.uniqlo.com/ut/ecm.asp
「素晴らしいジャケットデザインでも知られているECMレコードの中からユニクロが厳選したアルバムジャケットをTシャツにしました」の由。ぜんぶで24種類あります。3枚買うと安くなるというので、面白がって、さっそく3種類選んで買ってしまいました。
腹の出た中年男の写真で申し訳ないのですが、こんな感じです。


ちょっとした解説とデータが載った正方形のタグが付いてくるのも、紙ジャケみたいで楽しいです。


聴いたことがあって、嫌いじゃないアルバムで、デザインも面白いものということで2枚はすんなり決まったわけですが、もう1枚はちょっと迷いました。いちばん数の多いECMのジャレットは別に興味ないし、デザインのカッコいいアルバムは他にもいろいろありますよね。
一番人気はまちがいなくこれでしょうが、着るのはちょっと恥ずかしいかな。
http://store.uniqlo.com/large/u36523.html
投稿時間 : 21:47 個別ページ表示 | コメント (0) | トラックバック (0)
ジャズ・ピアニストで作曲家のアンドリュー・ヒルが亡くなった。なんてこった。
ディスクユニオン
http://blog1.musicfield.jp/du_ds2/archives/2007/04/andrew_hill_1.html
ブルー・ノート
http://bluenote.com/news.asp?NewsID=441
All About Jazz
http://www.allaboutjazz.com/php/news.php?id=13551
古巣のブルー・ノートに再復帰して、久々のメジャー配給アルバム『Time Lines』を出したばかりだった。それが世界的に賞賛され、日本でもミュージック・マガジン誌の年間ベストでジャズ部門の1位に選ばれたばかりだった(日本盤が出ていないのに!)。CD3枚分のピアノ・ソロ録音が発掘されたばかりだった。ネルス・クラインによるカヴァー・アルバムが出たばかりだった。
つまり、これまでになく話題を集め、活動が注視されていた、まさにその時に亡くなったのだ。
あるいは、数年前から闘病生活をおくっていたというから、2000年以降、毎年のように新作アルバムを出していたのは、先を急いでいたのかもしれない。いずれも評判が良かったのに、いつでも聴けるからと後回しにしていた私はバカである。

The Dusk (2000) Amazon.co.jp

Beautiful Day (2002) Amazon.co.jp

The Day the World Stood Still (2003) Amazon.co.jp

Time Lines (2006) Amazon.co.jp
フリー・ジャズとフュージョンという両極端からジャズに入ったせいか、じつはピアニストにあまり興味がない。好きなピアニストを問われても、セロニアス・モンクやセシル・テイラーは別格としても、数えるほどしかいない。アンドリュー・ヒルは60年代のブルー・ノートのアルバムは全部聴いているので、かなり好きだったと言えると思う。
家にあるもので何か聴こうと思ってレコード棚を探したのだが、いちばん新しいのが74・75年録音のフリーダム盤『Spiral』だったのには愕然。80年代のアルバムも一枚ぐらい持っていると思ったのだが……。これじゃ死を悼む資格などないかも。
投稿時間 : 23:15 個別ページ表示 | コメント (0) | トラックバック (0)
新宿ピットインで、ポール・ニルセン=ラヴ、ペーター・ブロッツマン、八木美知依のコンサートを見た。「びっくりゲストあり」と告知されていた4人目の演奏者が誰なのかという疑問は、開演前にブロッツマンと坂田明が談笑しながら歩いていたのであっけなく氷解。ブロッツマンの生演奏は5~6回、あるいはもっと見ていると思うので、いきなり姿を見ても感慨はなかったが、よく考えてみれば、レコードでもCDでもビデオでもなく演奏をじかに聴くのは、じつに23年ぶりのこと。こちらが20歳ぐらいの時からずっと第一線で活躍し続け、姿かたちにもあまり変化がないブロッツマンや坂田明は、やはり傑物なのだ。
企画・MCのマーク・ラパポートさんの前口上のあと、第一部はトリオで4曲を演奏。ブロッツマンはクラリネット、ソプラノ~テナー・サックスと持ち替え。八木は20絃箏と17絃箏のうち音の低いほう(たぶん17絃箏)を主に演奏していたと思う。ニルセン=ラヴのドラムは相変わらずソリッドで手数の多いもので、前のめりにハードにドライヴしながら、全体としては優雅にスウィングしているという、この人の特殊能力が最初から全開。小一時間のセットを集中して聴いて、もうこれ以上ないというぐらい堪能したのだが、坂田の加わった第2部はさらに輪をかけて凄かった。
まず、坂田とブロッツマンが並んで演奏している図が珍しくて嬉しくて、その上、2曲目の出だしで坂田がクラリネットに持ち替えると、ブロッツマンが取り出したのは何とアルト・サックス。目を閉じて聴いたら演奏者を間違えるかもと一瞬思ったが、出てくる音は紛うかたなきそれぞれのもので、個性は聞き違えようがない。途中で坂田がアルト・サックスに戻り、なんと日独巨匠のアルト合戦が実現。ブロッツマンのアルト演奏を聴くのは初めてだと思うが、低い音域を重く吹き鳴らすので、まったくアルトらしくないのが面白い。第1部よりも音量を上げて徹底抗戦する八木。細い体をしならせて一心不乱に爆音をまき散らすニルセン=ラヴ。いやもう、気がついたらずっと噛みしめていた奥歯が痛かったというぐらい、集団即興を聴く緊張感と楽しみに満ちた、期待を遙かに上回るステージでした。
ひとつ疑問に思ったのは各曲のエンディングで、何の合図も目配せもないのに、一丸となってドンッと終わることができるのは、どうやっているのだろう? レギュラー・グループではないだけに、息がぴったり合っているのが不思議だった。
ニルセン=ラヴは2005年4月の来日の時も、八木とのセッションとアトミックでの演奏を見たが、ジャズのコスプレみたいなアトミックよりも、こういうセッティングのほうが遙かに面白い。ラパポートさんによると、10月ごろザ・シングとして来日するかもとのこと。今から楽しみである。
このトリオが結成された昨年夏のノルウェーでの演奏がYouTubeにありました。
http://www.youtube.com/watch?v=rbxUGandqkc
投稿時間 : 04:56 個別ページ表示 | コメント (0) | トラックバック (0)
数日前にこのニュースを読んで以来、何かもやもやして仕方がないのだが、うまく考えがまとまらない。
HMVのニュース記事
http://www.hmv.co.jp/news/article/702070068
要するに、グレン・グールドの名盤『ゴルトベルク変奏曲』は1955年の演奏なのでモノラル録音であり、現代のオーディオ・ソフトとしてはいささか残念である。そこでこれを新開発のピアノ演奏解析ソフトで徹底的に調べて数値化し、最新鋭の自動ピアノをわざわざグールドが愛用したスタジオに持ち込んで演奏させ、それを5.1チャンネルなどの最新技術で録音したSACDがもうじき発売される――という話。
(ちなみにこのCDのことは、多年愛読しているこのサイトで知った)
「音楽中心日記」
http://www15t.sakura.ne.jp/~andy/diary/diary200702a.htm
もちろん、音楽に対する冒涜だぁ!とか言いたいわけではないし、記事も「ひとつの試みとして楽しんでほしい」というトーンなのははっきりしているし、煎じ詰めれば単なる自動ピアノのCDでしょ、とも思うのだが、何かすんなり胃の腑に落ちないものがある。
技術の変化に合わせて名曲・名演を再録音することは、ポピュラー音楽でもよくあることだし、グールドだって『ゴルトベルク~』のステレオ録音を遺している。また、こういうことは、スタジオにこもって、テープ編集を前提に多数のレコードを製作したグールドには、ぴったりの後日談なのではないか、という気もする。
(クラシック音楽にまったく疎い私がなぜグールドを知っているかといえば、実家の両親がよく聴いていたからである)
それでも何となくもやもやが晴れないのは、結局のところ、演奏者の不在というのが決定的に不気味だから――ではないかという気がしてきた。よくできた蝋人形を見ているような不気味さ。
それに、例えばこれをそうと知らずに聴かされたら、わからないのではないか? 解析ソフトの能力が限りなく向上して行ったら? 存命の演奏者が密かにこれを使ったら? また、いつの日か、ピアノ以外の楽器も精緻な自動演奏でシミュレートできるようになったら? 『ミントン・ハウスのチャーリー・クリスチャン』を新宿ピットインで再録音したら? などなど、くだらないと思いつつ、いろいろな可能性を考えてしまうのである。
しかしまあ、ジャズというのは一回性の音楽なので、これをやられたら不気味さはグールドの比じゃないよなあ、と思っていたら、ソフトを開発したゼンフ・スタジオの公式サイトを読むと、次はアート・テイタムのアルバムの発売が決定しているというではないか!
Zenph Studios の公式解説
http://zenph.com/sept25.html
そして今後もソニーBMGと共同でこの試みを続けていくということで、その次はなんとセロニアス・モンクという声もあるらしい。うひゃあ、それはいったい、どんな顔をして聴けばいいのでしょうか?
「グレン・グールドによるバッハ:ゴールドベルク変奏曲」の再創造(3/21発売)
Amazon.co.jp
投稿時間 : 23:39 個別ページ表示 | コメント (0) | トラックバック (0)